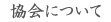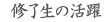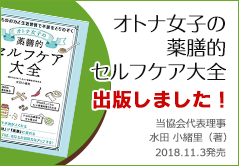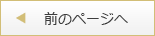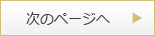HOME > お知らせ・コラム一覧 > 【薬膳コラム】端午の節句 菖蒲
<薬膳コラム>
2025年5月1日(木)
【薬膳コラム】端午の節句 菖蒲
国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子です。
5月5日は五節句のひとつである端午の節句で、
菖蒲の節句とも呼ばれています。
中国にならって奈良時代、
聖武天皇の頃から端午の節句に
菖蒲を使ったという記録があり、
平安時代には天皇に菖蒲を献上するなどの
行事が催されました。
六日の菖蒲とは、
5月5日の端午の節句の翌日の菖蒲を指し、
時機に遅れて役に立たないことに例えられます。
武士が台頭し、菖蒲の葉が剣の形に似ていることや
その音から菖蒲が尚武(しょうぶ)に転じて、
男の子の誕生を祝い立身出世を願って、
鯉のぼりを上げたり、
武者人形を飾ったりするようになりました。
現代では、この日はこどもの幸せをはかる
国民の祝日「こどもの日」に制定されています。
菖蒲は穂状の花を持つショウブ科の石菖蒲のことで、
古くはあやめと呼ばれていたので、
大きな花を咲かせるアヤメ科の花菖蒲や
あやめとは混同されがちで、
武者人形の傍にも、よく花菖蒲が飾られます。
中国最古の本草書である
神農本草経にも載っている石菖蒲(セキショウ)の根茎は、
体表の窓にあたる目、鼻、耳、口、尿道、
肛門の九つの竅(あな)を通じさせ、
意識をはっきりさせる開竅薬(かいきょうやく)であり、
芳香性健胃薬でもあります。
菖蒲の節句に今も残る風習のひとつが菖蒲湯です。
使用する菖蒲の葉は花屋さんやスーパーなどで購入できます。
アサロン、オイゲノールなど芳香性のある
精油を含む菖蒲の葉をお風呂に入れて、
香りを楽しみながら、ゆったりと湯船につかり、
身体を温めませんか。
心も身体もリフレッシュされることでしょう。
令和7年5月1日
薬剤師、国際中医師、国際中医薬膳師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子