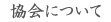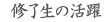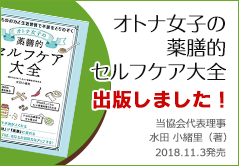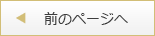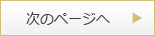HOME > お知らせ・コラム一覧 > 【薬膳コラム】紫蘇
<薬膳コラム>
2025年5月15日(木)
【薬膳コラム】紫蘇
国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子です。
和のハーブともいうべき紫蘇の原産は中国です。
日本への渡来は古く、
2500年前の土器と一緒に、
その種子が見つかったと伝え聞いています。
紫蘇という名前は、
中国の華佗(かだ)という名医が
蟹を食べて食中毒になった若者に
その植物を用いた紫色の煎じ薬を与えたところ、
若者は蘇ったことに由来します
お刺身などに青紫蘇が添えてありますよね。
紫蘇は解魚蟹毒といって魚介類に含まれる
毒素を消し去ってくれるので、
残さずに召し上がっていただきたいです。
梅干に赤紫蘇を入れるのは
赤く色付けするためだけでなく、
抗菌や防腐なども目的としています。
紫蘇(食性食味/温辛、帰経/肺脾)には、
体表にある邪気を払い除く、
寒さを消散させる、気を巡らせる、
中焦(脾胃)を温めて補い、
その働きを正常して穏やかにする、
体内の老廃物を排出する、
胎動不安を解消する作用があります。
本草綱目には、「蘇は、性は舒暢(のびるの意)で、
氣を行(めぐ)らし、
血を和するものだから蘇というのだ」という
記述があります。
日本各地で栽培され、
その品種は大きく赤紫蘇系と
青紫蘇系に分けられますが、
薬用としては葉の両面または
下面が紫色の赤紫蘇系のものを用います。
シソの葉および枝先を
基原とする生薬は蘇葉(そよう)と
呼ばれています。
蘇葉は気分がふさいで、
咽喉や食道部に異物感がある方の不安神経症、
神経性胃炎、つわり、咳、しわがれ声、
不眠症などに用いられる
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、
胃腸虚弱で神経質な方の
風邪の初期に効果がある香蘇散(こうそさん)などの
漢方薬に配合されています。
蘇葉は開花前の香気が強い葉を摘みます。
新しいもの、芳香の強いものが良品で、
あまり長く煎じてはいけないとされています。
青紫蘇を料理に使う時もなるべく新鮮なものを、
加熱は短めにあるいは生で召し上がるのが
よろしいかと思います。
気分が重かったり、落ち込んだりする時は、
紫蘇の香りを堪能して、
滅入る気持ちを解消してはいかがでしょう。
令和7年5月15日
薬剤師、国際中医師、国際中医薬膳師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子