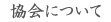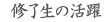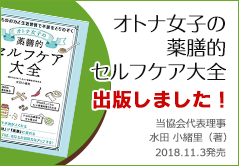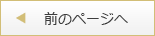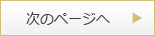HOME > お知らせ・コラム一覧 > 【薬膳コラム】西太后に学ぶ八珍糕①
<薬膳コラム>
2025年11月1日(土)
【薬膳コラム】西太后に学ぶ八珍糕①
国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子です。
中国清朝末期、72歳まで生きた権力者・西太后。
その養生法に興味を抱き、
彼女に仕えた徳齢の手記や「西太后の不老術」、
そして西太后と甥・光緒帝の処方集
「慈禧光緒医方選議」を読み進めています。
日々、体調がすぐれないこともあれば、
眠れぬ夜もある。気持ちが沈むことも、
親の介護や子どもの心配事に心を砕くこともある。
そんななかでも、動ける限りは仕事を続け、
家のことも少しはこなし、
時には自分の好きなことにも手を伸ばしたい。
そう願う私にとって、
「いつまでも若々しくありたい」
「老化に抗いたい」という思いは、
人生の大きな課題です。
「慈禧光緒医方選議(じきこうしょいほうせんぎ)」には、
補益の処方として「八珍糕(はっちんこう)」が
記されています。
「茯苓、蓮子(去心)、芡実、□□、扁豆、薏米、
藕粉各二両、□□五両、あわせてすり砕き、
極細粉末とし、白糖を加え、およそ一両ごとに分け、
糕とする。(□□は欠字)」と。
この処方は、明代の「外科正宗(げかせいそう)」
(陳実功/ちんじっこう)に記された
「八仙糕方」の加減であり、
もともとは小児の胃腸虚弱や消化不良、
食欲不振、腹部膨満、顔色の黄ばみ、痩せ、
脾虚による軟便や下痢などに用いられたもの。
健脾養胃・益気和中の効能があり、
西太后の体質にも合っていたと記されています。
茯苓(ぶくりょう)はマツホドの菌核で、
現代日本ではもっぱら医薬品として用いられます。
蓮子(れんし)はハスの種子で、
苦みのある芯は除きます。
芡実(けんじつ)はオニバスの成熟種子、
扁豆(へんず)はフジマメの成熟種子、
薏米(よくべい)はハトムギの種皮を除いた種子、
藕粉(おうふん)は蓮根のでんぷんです。
さて、「糕」とはどのようなものなのでしょうか。
清代に袁枚(えんばい)が編纂した「随園食単」には、
「糕とは穀粉を潤し、平たくのして蒸した食品の総称」とあります。
ういろうや羊羹もその一種とされ、
現代ならオーブンで焼くという手法もありかもしれません。
たとえば、大手パンメーカーが販売する
馬拉糕(マーラーカオ)は、
マレーシア由来の蒸しケーキで、
これも「糕」の一種ですね。
文献中の欠字「□□」には、
季節や体調に応じて加える素材が
選ばれていたのではないかと考え、
私は薬膳に精通した国際中医薬膳師の方々に相談しました。
糕のバリエーションは実に豊かで、
養生の知恵がそこに息づいています。
この続きは、11月15日掲載予定のコラムにてーー。
令和7年11月1日
薬剤師、国際中医師、国際中医薬膳師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子