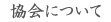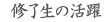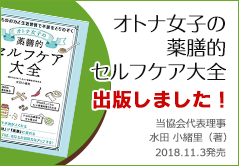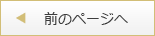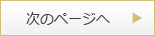HOME > お知らせ・コラム一覧 > 【薬膳コラム】西太后に学ぶ八珍糕②
<薬膳コラム>
2025年11月15日(土)
【薬膳コラム】西太后に学ぶ八珍糕②
国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子です。
中国清朝末期、72歳まで生きた権力者・西太后。
その養生法に興味を抱き、
彼女に関わる書物を読み進めています。
紫禁城で通訳兼女官として仕えた徳齢の著書
「西太后に侍して 紫禁城の二年間」によると、
西太后は独特の食生活を送っていました。
温かい料理:常に温かい料理を摂ることで、
身体の陰陽バランスを保ち、
気の巡りを整えることを重視していました。
豊富な品数:約150品もの料理(点心を含む)が並びました。
主菜だけでなく、小皿料理も豊富で、
栄養の多様性を確保すると同時に、
皇帝の威厳と豊穣さを象徴していました。
主な食材:豚肉、羊肉、野鳥、鶏や鴨などの家禽、
そして様々な野菜が中心でした。
牛肉は役畜として尊重されていたため、
食用にはされませんでした。
好みの調理法:皮つきの肉を好み、
脂と皮の風味を重視していました。
点心への愛:季節の果物、蓮の実、豆類の砂糖がけ、
胡桃など、料理よりも点心を好んでいました。
飲み物:菊花茶やジャスミン茶などの花茶を愛飲し、
その香りと見た目を楽しみながら、
気を整えていました。
午後の習慣:午後には砂糖湯を飲み、
神経を鎮めてから午睡を取るのが日課でした。
来賓へのもてなしは豪華な料理:
ふかひれや燕の巣などの高級食材を
ふんだんに使用し、外交的な場面では
豪華さを演出しました。
この記録から、
西太后は単に美食を追求するだけでなく、
健康や精神の安定、
そして権威を示すための手段として
食を捉えていたことが伺えます。
西太后が食していたという八珍糕は、
季節や体調に応じて加える素材が
選ばれていたのではないかと考え、
糕のバリエーションはさまざまだったと推察しました。
そこで私は夏の盛り、
米粉・米油・塩少々で生地を整え、
緑豆粉と甘酒を加えて蒸し菓子に仕立てました。
緑豆(食性食味:寒・甘/帰経:心胃)は、
暑熱による不快感を鎮め、余分な熱を冷まし、
体内の不要な水分を排出します。
甘酒(食性食味:温・甘辛/帰経:脾胃肺)は、
気を補い、津液を生じさせ、脾胃の働きを整え、
経絡を温めて血流を促し、排便を助けます。
高温多湿の季節に、
心身を癒やす養生の一品として取り入れました。

令和7年11月15日
薬剤師、国際中医師、国際中医薬膳師、
紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子