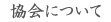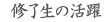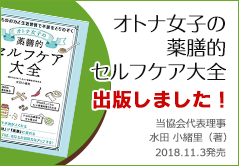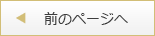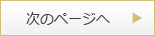HOME > お知らせ・コラム一覧 > お正月 雑煮
<薬膳コラム>
2019年1月1日(火)
お正月 雑煮
新年あけましておめでとうございます。国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師の伊東千鶴子です。
お正月の三が日にはおせちと雑煮をいただき、新年を祝います。本来、雑煮は神仏に供えた餅を下げて煮込み、
五臓を保養する「保臓」といわれていました。
?婚家の雑煮では昆布と煮干し、干し椎茸でだしをとって醤油で味を調えたすまし汁に食べやすい長さに切った
餅菜を加えて少し煮て、焼いた切り餅とかまぼこを入れたお椀に、餅菜の入った温かい汁を注ぎます。
軟らかい餅が好きな義父母は軽く焼いた餅を小鍋に取り分けた汁でさらに煮ていました。
餅菜は小松菜に似て非なるもので、正月菜とも呼ばれ、東海地方ではお正月を迎えるにあたって
欠かすことのできない食材でしょう。
?雑煮の作り方は地域や家庭によってさまざまで、醤油を使ってすまし汁のようにしたり、
白味噌あるいは赤味噌で仕上げたり、角餅か丸餅か、餅を焼くか煮るか、さらに入れる具材もいろいろです。
家庭の味が一番であったカレーライスのお店が全国展開したように、各地域の雑煮が食べられる
お店があってもよいように思えます。
?日本に住む私達が普段、主食とするうるち米は気を補い、消化吸収をつかさどる脾胃の働きを正常にします。
そして身体を温めも冷やしもせず、作用が穏やかで、毎日摂取しても特別な注意をはらう必要もなく、
気軽に食することができる平性の食物です。そばやパン、うどんなどの原料となる小麦にはやや身体を
冷やす性質があります。餅米はうるち米と同様、気を補い、脾胃を補い、さらに身体を温める温性の食物です。
寒いこの時期に餅の入った温かい雑煮を食べると、身体を温めることで内臓も温まり、その働きも活発になるので、
「保蔵」と呼ばれるのも納得できますね。
?皆様が今年一年、心も身体も健やかでありますようにお祈り申し上げます。
平成31年1月1日
国際中医師、国際中医薬膳師、薬剤師、紡ぐしあわせ薬膳協会認定講師 伊東千鶴子